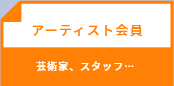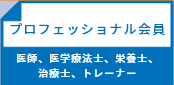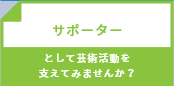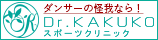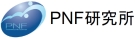芸術活動をおこなっていると、稽古場での練習中の怪我や不調、劇場での利用者や観客の怪我や急病など、専門家に引き継ぐまでの救護(応急処置)がおこなえたほうがよい場面があります。そんな時にあわてず対処できるよう必要なものを日頃から準備して、置き場や使い方を周知しておきましょう。
STEP1
どんな人がどのようなことを行う場なのか、施設規模・環境はどのくらいかによって、どんなリスクがあるか具体的に想定します。
- 個人の稽古場なら →指導者、生徒の 捻挫、骨折、打撲、立ちくらみなど
- 不特定多数が集まるスタジオ・劇場・施設なら →利用者、出演者、観客の怪我や不調、急病
→捻挫、打撲、切り傷、鼻血、気分不良、意識喪失など
STEP2
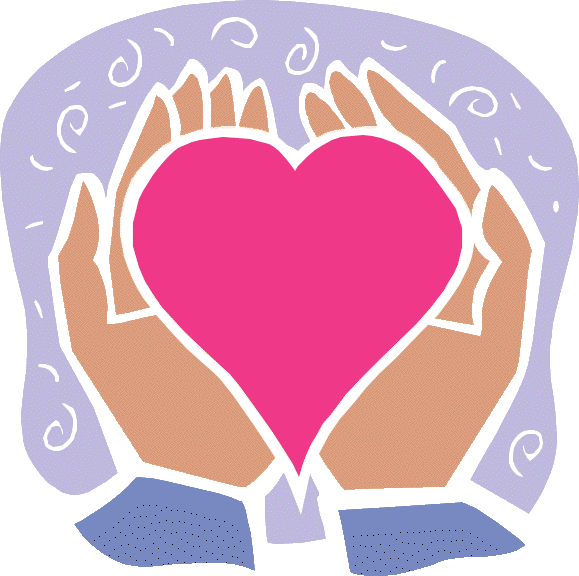
想定されるリスクに対して備えておくべきもの、設置場所を決めます。施設規模によっては、複数個所に備え付けるのもよいでしょう。
- (1) 外傷(骨折・ねんざ・切傷など)の手当てに □包帯 □ガーゼ □テープ □絆創膏 □ピンセット
- (2) 移送に □車椅子(担架や運びやすい椅子や板などの代替もあり)
- (3) 保温に □使い捨てカイロ □毛布 □タオルケット
- (4) 身体を休める □簡易ベッド □枕 □毛布 □バスタオル
- (5) 救命処置に(心臓と呼吸が止まってしまった場合) □AED(近くのAEDの場所を確認しておく。公共施設は設置義務あり。)
□ゴム手袋(血液にさわらないように)
□ビニール袋(持ち手がついているスーパーの袋で可)
□氷(冷凍庫があれば) □アイスバッグ(ファスナーつきビニールバッグで代用可)
□三角巾 □タオル □副木(段ボールや雑誌で代用可) □湿布薬
STEP3 救護(応急処置)の原則
- 1. 投薬はおこなわない
→体質がわからないので危険。利用者が不特定多数の場合は、原則として内服薬は常備しない。 - 2. 意識がない、頭部を強打し嘔吐・吐き気や大量出血
→すぐに救急車(専門家)を呼ぶ - 3. 救命処置や応急処置を行うとき
→周囲の安全を確認。道路や階段では、救護する人にも危険が及ぶため、まず平坦な場所へ移動を。
最後に

救護(応急処置)に使うものは清潔でなければなりません。定期的にチェックしていつでも使えるようにしておきましょう。
制作:NPO法人芸術家のくすり箱 監修:齋藤明子(ヘルス&ライフサポートTAK 代表) [2012.4作成]